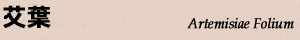  |
|
| 【 ガイヨウ 】 |
 『本草綱目』に「艾は疾を乂(おさ)め得るもので、久しく經たものほど善い。故に文字は艾に従ふのだ…、醫家これを用ゐて多くの病に灸するから灸草といふ…凡そ艾葉を用ゐるには、久しく置いた古いものを修治して細軟にして用ゐねばならぬ…」と解説があり、古代から薬用植物、食用植物として重要であり、鑑賞用としても知られる。薬能は本草に記述があるように吐血、鼻血、子宮出血などの止血薬として、また胃炎、胃潰瘍に、解毒作用、動脈硬化や高血圧の予防に利用されるとともに、精油成分を利用して皮膚を適度に刺激して保温効果を高め、腰痛や冷えによる関節の痛み、腹痛などを治し、また香りによる心身をリラックスさせる効果に外用薬として、さらには入浴剤で腰痛、関節痛に効果があるとされるなど民間薬的使用法が知られ、子宮出血、痔出血、肛門からの出血などに応用される 『本草綱目』に「艾は疾を乂(おさ)め得るもので、久しく經たものほど善い。故に文字は艾に従ふのだ…、醫家これを用ゐて多くの病に灸するから灸草といふ…凡そ艾葉を用ゐるには、久しく置いた古いものを修治して細軟にして用ゐねばならぬ…」と解説があり、古代から薬用植物、食用植物として重要であり、鑑賞用としても知られる。薬能は本草に記述があるように吐血、鼻血、子宮出血などの止血薬として、また胃炎、胃潰瘍に、解毒作用、動脈硬化や高血圧の予防に利用されるとともに、精油成分を利用して皮膚を適度に刺激して保温効果を高め、腰痛や冷えによる関節の痛み、腹痛などを治し、また香りによる心身をリラックスさせる効果に外用薬として、さらには入浴剤で腰痛、関節痛に効果があるとされるなど民間薬的使用法が知られ、子宮出血、痔出血、肛門からの出血などに応用される 帰膠艾湯に配剤される。基原はヨモギArtemisia princeps Pampanini及びヤマヨモギA. montana Pampaniniの葉及び枝先である。ヨモギは本州、四国、九州に広く分布し、道端や山野、荒れ地などに自生する多年生草本で、茎は高さ50〜120cm、上方で分枝する。8〜10月頃に茎頂より花穂を出し、総状に小さな管状花からなる頭花をつける。全体に香気がある。新芽を草餅に供し、葉の裏毛からもぐさを作り、5月の端午の節句にはショウブと共に浴湯に入れられる。ヨモギはもえぎで良く燃える木という意味である。 帰膠艾湯に配剤される。基原はヨモギArtemisia princeps Pampanini及びヤマヨモギA. montana Pampaniniの葉及び枝先である。ヨモギは本州、四国、九州に広く分布し、道端や山野、荒れ地などに自生する多年生草本で、茎は高さ50〜120cm、上方で分枝する。8〜10月頃に茎頂より花穂を出し、総状に小さな管状花からなる頭花をつける。全体に香気がある。新芽を草餅に供し、葉の裏毛からもぐさを作り、5月の端午の節句にはショウブと共に浴湯に入れられる。ヨモギはもえぎで良く燃える木という意味である。 |
|