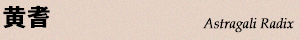  |
|
| 【 オウギ 】 |
 基原植物として公認される種類はナイモウオウギAstragalus mongholicus Bunge及びキバナオウギA. membraceus(Fisch)Bungeの2種類。漢薬名は黄耆と書くが、李時珍は「耆は長(オサ)の意味で黄耆は黄色のもので補薬としての長だからかく名付けたもの」と解説している。ナイモウオウギは山西省、黒龍江省、内蒙古等を主産に生産される多年生草本。茎は直立し高さ50〜150cm。6〜7月頃総状花序を腋生。11〜12月、葉が枯れた頃根が充実し収穫する。『重修本草綱目啓蒙』に「根軟クシテ綿ノ如キモノヲ綿黄耆トス上品ナリ、綿ノ字ハ柔軟ニシテ綿ノ如キヲ云ウ…」と解説がある。生薬は形が長く肥大し、柔靱で、外面は淡黄褐色或は黄褐色、不規則な縦じわがあり、横切面は淡黄色〜黄白色で褐色の形成層輪が環状に通っていて甘く、芳しい香りをもつナイモウオウギが優良品として扱われる。主要成分アストラガロサイドを産し、収穫時期で種類別に比較し、ナイモウオウギに高い含有を示すことが確認された。身体虚弱、皮膚栄養不良で皮膚及び皮下に水毒停滞するを治す一種の強壮性止汗利尿薬である。市場に晋耆或いは紅耆と称し、外面が紅褐色〜紫褐色、横切面黄色の繊維が目立つ、甘味の強い類似の生薬が見られるが、日本の公定書では認めていない。師部、木部が発達し、シュウ酸カルシウムの単晶を細胞に含み、結晶細胞列を呈し、明らかに黄耆とは識別される。 基原植物として公認される種類はナイモウオウギAstragalus mongholicus Bunge及びキバナオウギA. membraceus(Fisch)Bungeの2種類。漢薬名は黄耆と書くが、李時珍は「耆は長(オサ)の意味で黄耆は黄色のもので補薬としての長だからかく名付けたもの」と解説している。ナイモウオウギは山西省、黒龍江省、内蒙古等を主産に生産される多年生草本。茎は直立し高さ50〜150cm。6〜7月頃総状花序を腋生。11〜12月、葉が枯れた頃根が充実し収穫する。『重修本草綱目啓蒙』に「根軟クシテ綿ノ如キモノヲ綿黄耆トス上品ナリ、綿ノ字ハ柔軟ニシテ綿ノ如キヲ云ウ…」と解説がある。生薬は形が長く肥大し、柔靱で、外面は淡黄褐色或は黄褐色、不規則な縦じわがあり、横切面は淡黄色〜黄白色で褐色の形成層輪が環状に通っていて甘く、芳しい香りをもつナイモウオウギが優良品として扱われる。主要成分アストラガロサイドを産し、収穫時期で種類別に比較し、ナイモウオウギに高い含有を示すことが確認された。身体虚弱、皮膚栄養不良で皮膚及び皮下に水毒停滞するを治す一種の強壮性止汗利尿薬である。市場に晋耆或いは紅耆と称し、外面が紅褐色〜紫褐色、横切面黄色の繊維が目立つ、甘味の強い類似の生薬が見られるが、日本の公定書では認めていない。師部、木部が発達し、シュウ酸カルシウムの単晶を細胞に含み、結晶細胞列を呈し、明らかに黄耆とは識別される。 |
|